青い海で波に乗る姿に憧れを抱きつつも、泳ぎへの苦手意識が大きな壁となり、一歩を踏み出せないでいる方は少なくありません。
 かえでちゃん
かえでちゃん
しかし、結論から言えば、適切な知識と準備があれば、泳げなくてもサーフィンを体験することは可能です。
ただし、安全にサーフィンを楽しむには水泳能力を身につける必要性があり、推奨はできません。
本記事では、泳げなくてもサーフィンを始められる理由、安全を確保するためのルール、海の危険性や対処法までを網羅的に解説します。
 まさとくん
まさとくん
- 「泳げない=サーフィンができない」わけではない
- 泳げなくてもサーフィンは楽しめるが、リスク管理が重要
- 泳げない人はパニックに陥らないことが重要
- 足がつく遠浅の海を選ぶ
- サーフィンスクールに通いプロから学ぶ
- 離岸流などの海の危険や安全対策を知ることが大切
目次
泳げなくてもサーフィンは始められるがリスク管理が必要
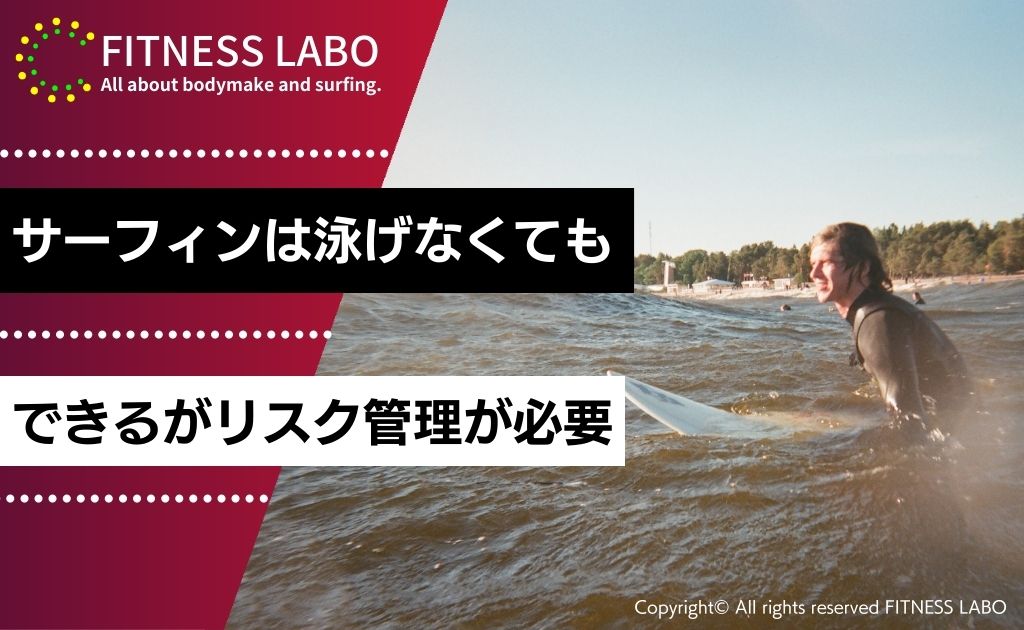
サーフィンと水泳能力は密接に関連しているように思われがちですが、必ずしも「泳げない=サーフィンができない」というわけではありません。
 まさとくん
まさとくん
ここでは、なぜ泳げなくてもサーフィンは始められるのか、そして「泳げない」ことによる心理的なリスクについて解説していきます。
泳げなくてもサーフィン体験ができる理由
泳ぎに自信がない人でもサーフィンができる最大の理由は、初心者が練習する環境が徹底的に管理されているためです。
 まさとくん
まさとくん
サーフィンスクールが提供する体験レッスンの多くは、安全性が確保された以下のような条件下で行われます。
- 基本的に足がつく遠浅の海
- 専門的な知識を持つプロのインストラクターが常に付き添う
レッスンは基本的に足がつく遠浅の海
インストラクターは、受講者が常に安心して立てる水深のエリアを選びます。
 かえでちゃん
かえでちゃん
深い場所へ行く恐怖を感じることなく、ボードに立つという基本的な動作に集中できる環境が整えられています。
サーフィンに必要なパドリング(ボードに腹ばいになって手で漕ぐ動作)やテイクオフ(ボードの上に立つ動作)といった基本スキルは、足がつく浅瀬で十分に練習でき、これらは必ずしも高い水泳能力を必要としません。
専門的な知識を持つプロのインストラクターが常に付き添う
泳げない参加者に対しては、水中での安全性確保を最優先に考えた指導を行います。
 まさとくん
まさとくん
「泳げない」不安が引き起こすリスクとは
泳げない人がサーフィンに挑戦する際、物理的な危険性以上に注意すべきなのが、心理的なリスク、すなわち「パニック」です。
管理された安全な環境であっても、「もし溺れたらどうしよう」という不安は、時として冷静な判断を奪う最大の敵となり得ます。
この不安感は、常に精神的な負担となり、サーフィンを心から楽しむことを妨げます。
 かえでちゃん
かえでちゃん
足がつく浅い場所であっても、予期せぬ落水による衝撃と恐怖心から、「立てば大丈夫」という単純な事実を忘れ、無我夢中で手足をばたつかせて体力を消耗してしまうケースがあります。
したがって、泳げない初心者がまず克服すべきは、泳ぎの技術そのものよりも、「水に落ちても冷静さを保つ」というメンタルの訓練です。
 まさとくん
まさとくん
泳げない人がサーフィンを安全に楽しむための3つの鉄則

泳げなくてもサーフィン体験は可能ですが、それは無条件ではありません。
安全を確保するためには、絶対に守るべきいくつかの「鉄則」が存在します。
- 鉄則1:場所選びを徹底する – 足がつく遠浅の海を選ぶ
- 鉄則2:信頼できるスクールでプロの指導を受ける
- 鉄則3:道具を正しく選び、管理する
 かえでちゃん
かえでちゃん
鉄則1:場所選びを徹底する – 足がつく遠浅の海を選ぶ
サーフィンにおける安全確保の9割は、場所選びで決まると言っても過言ではありません。
特に泳げない人にとって、どこでサーフィンをするかという選択は、他のどんな要素よりも重要です。
 まさとくん
まさとくん
初心者が選ぶべきサーフスポットには、以下の明確な基準があります。
- 海底が砂地で、足がつく遠浅のビーチであること(ビーチブレイク)
- 波が穏やかで小さいこと
- 人が密集していないこと
海底が砂地で、足がつく遠浅のビーチであること(ビーチブレイク)
砂地の海底は、ボードから落ちた際の衝撃を和らげ、怪我のリスクを大幅に低減します。
何よりも、常に足がつくという事実は、「溺れるかもしれない」という根本的な恐怖を取り除き、安心して練習に集中させてくれます。
波が穏やかで小さいこと
膝から腰程度の高さの波が理想的です。
 まさとくん
まさとくん
逆に、胸以上の高さの波は、足がつく場所であっても危険を伴うため、絶対に避けるべきです。
人が密集していないこと
人気のサーフポイントは混雑しがちですが、初心者は他のサーファーとの接触事故を避けるためにも、比較的空いている場所を選ぶべきです。
 かえでちゃん
かえでちゃん
これらの場所を選ぶという行為は、単なる場所決めではなく、積極的なリスク管理の一環なのです。
鉄則2:信頼できるスクールでプロの指導を受ける
自己流や、サーフィン経験のある友人からの指導で始めるのは、絶対に避けるべきです。
特に泳げない人にとって、サーフィンスクールのレッスンを受けることは、安全を確保するための必須事項です。
 まさとくん
まさとくん
質の高いサーフィンスクールを選ぶことは、自身の安全を専門家に委託することを意味します。
良いスクールは、レッスン料の中に以下のような重要なサービスを含んでいます。
- 徹底した安全講習
- 適切な用具の提供
- インストラクターによる常時監視
- 万が一の事故に備えた傷害保険
レッスン前には、その日の海のコンディション、守るべきルール、緊急時の対処法などについて詳細な説明があります。
初心者の安全のために設計された、表面が柔らかい素材でできたソフトボードや、体格に合ったウェットスーツなど、安全性の高い装備をレンタル可能です。
 かえでちゃん
かえでちゃん
また、スクールを選ぶ際は、日本サーフィン連盟(NSA)公認のインストラクターが在籍しているか、ウェブサイトなどで安全管理体制について明確に記載されているか、そして泳げない人への対応実績が豊富かなどを確認すると良いでしょう。
鉄則3:道具を正しく選び、管理する
それぞれの道具が持つ安全上の役割を正しく理解し、適切に管理することは、ボードの上に立つ技術を学ぶのと同じくらい重要です。
特に重要なのが、サーフボードと足首をつなぐ「リーシュコード」です。
これは単なる流れ止めではなく、安全性を高める上で重要な道具です。
万が一波に巻かれても、リーシュコードがあれば、大きな浮力を持つサーフボードを手元に引き寄せることができます。
 まさとくん
まさとくん
ただし、リーシュコードは「命綱」ではないことを覚えておく必要があります。
リーシュコードに頼らず、リスクマネジメントを徹底することが何よりも重要です。
また、ウェットスーツも、体温維持という主な機能に加え、浮力を補助したり、クラゲなどの有害生物や海底との接触から皮膚を保護したりする役割があります。
「泳げない」からこそ知るべき安全知識

サーフィンは自然を相手にするスポーツです。
特に泳ぎに自信がない人は、海の潜在的なリスクをより深く、そして正確に理解しておく必要があります。
ここでは、以下の項目について、それぞれ知っておくべき必須の安全知識を解説します。
- 水難事故の最大の原因である「離岸流」
- リーシュコードが切れた場合の対処法
- そのほかの予期せぬトラブル
水難事故の最大の原因である「離岸流」
海に潜む危険の中で、最も注意すべきものが「離岸流(リップカレント)」です。
 かえでちゃん
かえでちゃん
離岸流の最も恐ろしい特徴は、一見するとその場所が穏やかで安全そうに見えることです。
流れが発生している場所は、周囲よりも波が砕けにくく、静かな海面に見えることがあります。
しかし、その下では強力な沖への流れが発生しているのです。
 まさとくん
まさとくん
- 周囲と比べて波が立っていない場所
- ゴミや泡が沖に向かって帯状に流れている場所
- 海水が濁り、周りと色が異なって見える場所
もし離岸流に巻き込まれてしまった場合、絶対にやってはいけないのが、パニックに陥り、岸に向かって必死に泳ぐことです。
 かえでちゃん
かえでちゃん
正しい対処法は、まず落ち着くことです。そして、岸と平行に(横方向に)泳ぐことです。
離岸流は川のように幅が限定されているため、横に移動すればいずれ流れから脱出できます。
万が一離岸流に流されても、絶対にボードを手放してはいけません。
ボードにしっかりとしがみつき、パドリングで岸と平行に移動します。
 まさとくん
まさとくん
リーシュコードが切れた場合の対処法
適切にメンテナンスをしていても、想定外の強い力でリーシュコードが切れてしまう可能性はゼロではありません。
 かえでちゃん
かえでちゃん
命綱であるボードを失い、自力で岸に戻らなければならない状況に陥るからです。
リーシュコードが切れたと認識した瞬間に取るべき行動は、以下の通りです。
- 何よりもまずパニックを抑えること
- 現状を把握すること
- 助けを求めること
恐怖心から無駄に手足を動かすと、急激に体力を消耗します。
まずは落ち着いて、呼吸を確保することが最優先です。
岸までの距離はどれくらいか、自分のいる場所は足がつく深さか、周りに他のサーファーはいるかなどを冷静に確認します。
 まさとくん
まさとくん
一つの失敗が致命的な結果にならないよう、すべてのルールを遵守することが極めて重要です。
そのほかの予期せぬトラブル
離岸流や装備の故障といった重大なリスクの他にも、海には注意すべきトラブルや生物が存在します。
これらについて知っておくことは、無用な不安を減らし、冷静に対処する助けとなります。
 かえでちゃん
かえでちゃん
特に混雑したポイントでは、ボード同士がぶつかったり、人の上にボードが乗ってしまったりする事故が起こり得ます。
「一つの波には一人しか乗ってはいけない(ワンマン・ワンウェイブ)」といった基本的なルールとマナーを守ることが、事故を防ぐ上で不可欠です。
 まさとくん
まさとくん
海の生物について、注意すべきは、クラゲ、エイ、ガンガゼ(ウニの一種)といった生物です。
特に夏場はクラゲが多く発生します。
 かえでちゃん
かえでちゃん
これらのリスクを正しく理解し、予防策を講じることが、安心して海を楽しむための鍵となります。
まとめ:「泳げない」から始めるサーフィン、その先へ

ここまで、「泳げない」という不安を抱えながらも、どうすれば安全にサーフィンを始められるかについて、具体的な方法と知識を解説してきました。
泳げないことは、サーフィンへの挑戦を諦める理由にはなりません。
正しい知識を身につけ、信頼できるプロの指導のもと、管理された環境で始めることで、誰でも波に乗る感動を安全に味わうことができます。
ただし、サーフィンを安全に楽しむには、最低限の水泳能力は身につけることを推奨します。
信頼できるサーフィンスクールを探し、初心者向けの穏やかなビーチで、まずは一度、波の上に立つという経験をしてみてください。
サーフィンは単なるスポーツではなく、自然との対話であり、新しい自分を発見する旅でもあります。
 まさとくん
まさとくん

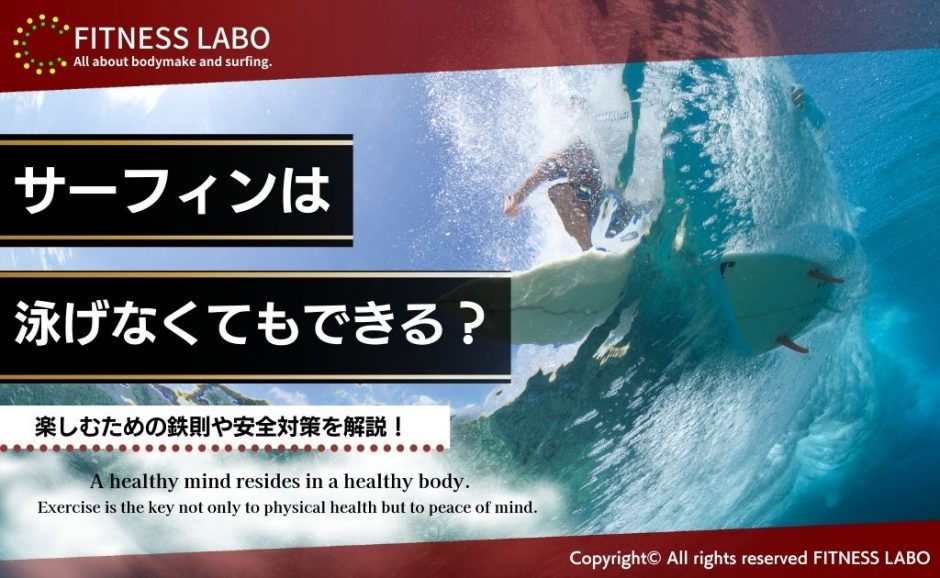



コメントを残す